現在上演されるオペラってどヘンデルの時代以降のものが多いです。
じゃあヘンデルの前はなかったのか?っていうとそういうわけではないんですが、あまり今は上演されないですね。
そもそもですけど、オペラって1600年ごろが最初って言われているんですけど、その前の時代は
ルネッサンス期と呼ばれる時期です。ルネッサンスって学校で習いましたね。
古典の復古とか復活とか言われていた時代です。
このルネッサンス期にモノディっていう独唱に伴奏をつける形式が出てきたのですが、それが今のオペラの原点になったと言われているのです。
オペラって重唱もあるけど基本的には一人が歌って、それに伴奏がつきますよね。
それならそもそもオペラって何?はっきりした線引きってなんなのか、どこからオペラでどこからオペラじゃないのって思うのですが、そこら辺をハッキリ区切りをつけるのって難しいんじゃないかと思います。
なんでもそうですけどいきなり変わるわけじゃないですしね。時代の流れとかいろいろあるので…。
初期のオペラと呼ばれているものを見るとこれもオペラかあ、なんだか朗唱っていう感じだなあ‥
と思うし、モノディに対する言葉がポリフォニーでポリフォニーは複数の独立したパートがあるのですが、
じゃあリゴレット第三幕の4人で全く違うことを歌う場面がありますけど
あれはなんなんだろうとか、ちょっと考えたりしちゃいます。
まあ難しい音楽理論的には違うのでしょう。
と…ごちゃごちゃ書いてしまいましたが、いずれにしてもジュリオ・チェーザレはヘンデルのオペラの中でも最も有名な作品ではないかと思います。
いったいどんなオペラなのかについて探ってみたいと思います。
ジュリオ・チェーザレってどんなオペラ?
ジュリオ・チェーザレっていうのはイタリア語読みです。
ラテン語読みだとユリウス・カエサル、また英語読みだとジュリアス・シーザー。
私なんかはジュリアス・シーザーで覚えていました。
ヘンデルがこのオペラを初演したのは1724年、39歳の時です。
原作はアントニオ・サルトーリオという人が作曲した「エジプトのジュリオ・チェーザレ」というオペラです。
原作はヘンデルが生まれる前に既にあった作品で、
つまりヘンデルのジュリオ・チェーザレには元になっているオペラがあるっていうことなんです。
今だったらちょっと問題になりそうなやり方ですが、当時は別に問題ではなかったんですね。
ヘンデルという人はドイツ生まれなのですが、イタリア式のオペラを勉強して、それをロンドンで開花させた人と言っていいと思います。
ジュリオ・チェーザレはそんなヘンデルがロンドンで発表したオペラの一つです。
でもってその頃ってヘンデルにとってどういう時期かっていうと
1720年に貴族達によるオペラの会社「王室音楽アカデミー」を設立、ヘンデルはその中の重要な一人でした。
当時はやはりオペラは貴族のものだったんですね。
このアカデミーは経営がずさんだったこともあり、8年で倒産してしまいますが
1724年というとまだこの王室音楽アカデミーがあってヘンデルは中心的な存在として活躍していた頃です。
実は歴史的に見るとイギリスってあんまりオペラが盛んじゃない国なんですよね。
オペラ作曲家もあまりいないし。
近代になるとブリテンがでてきますけどそれは20世紀になってからのこと。
唯一ヘンデルがイギリスに住んでいた18世紀前半だけがいっときイタリア式のバロックオペラが栄えたのかなと、そんな印象です。
そのあとは乞食オペラっていうのが出てきて一気に押されちゃうんですけどね。
なぜサルトーリオのオペラを使った?
オペラって神話が元になっていたり、戯曲が元になっていたり、またはワーグナーのように作曲家自身が考えたりといろんなケースがあるのですが、
ジュリオ・チェーザレの場合の原作はちょっと不思議なんですよね。
原作:ジャコモ・フランチェスコ・ブサニ台本、アントーニオ・サルトーリオ作曲オペラ「エジプトのジュリオ・チェーザレ」。
ん?なにこれって最初思ったんですよね。
オペラが元になったオペラなの?と。
この時代は著作権云々とかそういうのもない時代ですし、曲の使いまわしなんかもやっていたので
オペラをもとにしてまたオペラを作るっていうことも普通にあったんだろうか、もしかしてそうなんだろうなあと。
元のオペラの旋律なども使ったりしていたりして(自分の作品ではないからそれはないかな。ロッシーニなんかはそういうのがよくあったみたいですけど)。
それと同時に思ったのは、ヘンデルはなぜこのオペラをもとにしたのかということ。
この原作のサルトーリオっていう作曲家は、実は1670年頃のヴェネチアでは有名な大作曲家でした。
オペラはフィレンツェで始まって→ヴェネチアで盛んになって→その後ナポリに移行する、という大きな流れがあって、ナポリ時代はまさに黄金のバロックオペラの時代と言っていいと思います。カストラートなんかがいたころですね。
1670年頃っていうのはその黄金時代よりも前なので、おそらくヴェネチアで一番オペラが盛んだったころだと思うのです。
まさにサルトーリオはその頃の作曲家だったようです。
サルトーリオの「エジプトのジュリアス・シーザー」は、1676年にヴェネチアで初演されて当時大成功だったオペラなんですよね。
今は全く知られていませんけど。
で、このサルトーリオっていう人ですが、ドイツのハノーファーというところでも活躍していた人なのです。
そしてヘンデルも時期はもっと後ですけどハノーファーの宮廷楽長だったことがあります。
これって偶然なんだろうか…。
ハノーファーにはサルトーリオのオペラの履歴が残っていたのかもしれない。
というよりハノーファーの宮廷で上演されていたのかもしれない。
それでこの作品をもとにアレンジしたくなった?
とそんなことを勝手に考えちゃったんですよね。よくある私の妄想です(笑)。
余談ですがハノーファーといえば日本の指揮者、大植英次さんがハノーファーのオーケストラの首席指揮者になったことで日本でも有名になった場所でした。
原作のジャコモ・フランチェスコ・ブサニっていう人ですが、この人もヴェネチアで活躍した台本作家です。
サルトーリオのオペラについてもいくつか台本を担当していたようですね。
バロック全盛期の時代のさらに昔、ヴェネチアの頃のオペラの世界ってあんまり情報が無いしオペラの上演もその時代というとモンテヴェルディのオペラくらいかなあ、でも他にもちゃんとオペラはきっとたくさんあって、
それが受け継がれたのかもしれないって思うとなるほどねえと思ったわけです(フフ)。
ヘンデルのジュリオ・チェーザレから始まってそこら辺の時代のことが少しだけ垣間見れた気がして、勝手にわくわくしちゃったのでした。
ジュリオ・チェーザレ簡単あらすじなど
ではジュリオ・チェーザレの簡単あらすじと見どころやポイントをざっと書いておこうと思います。
何と言ってもシーザーのストーリーで、歴史的なお話が絡むので歴史に詳しい人はおもしろいかと思います。
クレオパトラも出てくるし、ポンペイウス(オペラではポンペオ)も出てくるオペラです。
歴史上の知っている名前が出てくるってオペラでは嬉しくないですか?
私などはそれだけで嬉しい方です(笑)。
ジュリオ・チェーザレに出てくるクレオパトラは美しさより野心満々の女性で、弟のエジプト王を退けて自分が王位につきたいと思う女性。
またポンペイウスという人は歴史的にもエジプトに裏切られる形で殺されちゃう戦士ですが、そこはオペラでも同じです。
クレオパトラは美貌で有名ですが、このオペラでは夫を殺された妻のコルネリウスも美人でやたらもてちゃう役。
美女が二人いるわけですね。
コルネリウスはエジプト王やその臣下にやたら言い寄られる女性です。
シーザーは歴史上でもポンペイウスが殺された時、敵ながら泣いたとされますが、それはこのオペラでも同様で、
なかなか良い話も入っています。
ポンペイウスって何度か結婚してますがそのうちの一人はシーザーの娘だったりするんですよね。
なんとなく、敵ながら友でもあるというあたりは日本の武士道にもちょっと通じるというか。
まあその辺はオペラではあまりわかりませんが…(笑)
でもまあそういうストーリーのおもしろさも人気の所以なのかもと思います。
ただし結構場面が変わるので、もう?と思うところもちょっと否めないかも。
あとバロックオペラはだいたいそうですが、時間が長め。油断していくと「え、そんな長いの?!」と思うかも。
バロックオペラはあくまで私のイメージですが、1幕がちょっと退屈で、2幕以降で盛り上がり始めるパターンが多い気がする中で、ジュリオ・チェーザレは比較的1幕もおもしろいかなと思います。
助かると思った夫が殺されて首が運ばれてきたりしますから、「え?これからどうなるの!」と思うわけです。
ヘンデルは全体に音楽とかレチタティーヴォが比較的重厚で聴きごたえは十分。バロックオペラがほとんど残っていない中でヘンデルってやっぱり音楽が良いのねえと思います。
ただアリアが長いんですよね。
終わったかと思うとまた繰り返しっていう感じ(笑)。この時代の特徴だから仕方ないかなあ。
合唱は最初と最後だけ、あとは一人が歌うのみ。この時代のオペラって2重唱とか3重唱もほぼ無いんですよね。
あとバロックはだいたいそうなんですけど、男性の役を女性がやったり男性がやったり、あるいはカウンターテナーがやったりなど、公演によっていろいろです。
ジュリオ・チェーザレの場合で言うとシーザー役は男性がやるのか女性がやるのかから始まって、それともカウンターテナーかなとか、いろんなパターンが考えられるのと、
時代的になのかみんながスカートっぽいのを履いていたりするので、衣装だけでは男女の区別も難しく「この人は男性?女性?どっちだ?」の判別から私は入ります(笑)。そこがワンクッションバロックの難しさだよねって思ってます。
<簡単あらすじ>
ローマの内戦でポンペオの軍を破ったシーザー。
ポンペオはエジプト王(クレオパトラの弟)のところに逃げますが、裏切られてポンペオは殺されてしまいます。
それを知らずポンペオの妻コルネリアとシーザーが和睦の話をしている時に
殺されたポンペオの首が届いたので、シーザーは怒り、コルネリアは失神してしまいます。
そして息子のセストは仇討ちを誓います。
一方シーザーとクレオパトラは互いに惹かれる仲に。
またコルネリアは夫の敵であるエジプト王とその臣下に言い寄られてしまい(美しいって罪です)
クレオパトラは実は弟の王座を狙っており、復習を誓うコルネリアとセスト親子に助力を申し出るという微妙な関係へ。
そしてクレオパトラの軍と弟の軍は戦いますが結果クレオパトラは負けて捕らえられてしまいます。
それを助けに行くシーザー。
そして相変わらずコルネリアに言いよるエジプト王ですが、息子セストが現れ父の敵とばかりエジプト王を殺します。
シーザーはセストを英雄と讃え、クレオパトラを王として冠を捧げ、皆が歓喜のうちにおわります。
見どころとしては第二幕でクレオパトラが歌う「優しい瞳をたたえて」のアリア。
とても綺麗なアリアなので注目したいところですね。
ちなみにモーツァルトが作ったオペラセリアに皇帝ティートの慈悲というのがあり、そこにもセストという若者が出てきますが、
こちらは同じローマでももう少し時代が新しいので別人ですね。
あとヘンデルは何度か変更を加えつつこのジュリオ・チェーザレを上演しています。
だからいくつかの版があるはずですけどそこまではきっとわからないかと思います。
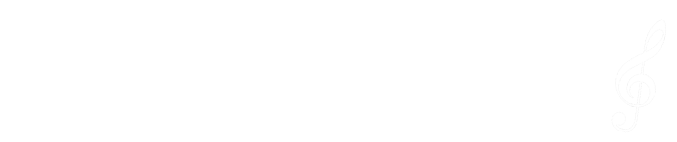

コメントを残す