オペラセリア(opera-seria)とは、日本語で言うと正歌劇。
18世紀のイタリアを中心に発達したオペラの形式です。
18世紀当時多くのオペラセリアが作られたのですが、現在まで上演されている演目は非常に少ないのです。
オペラセリアの特徴
オペラセリアのセリアは、英語だとシリアス(seriousu)、まじめなとか真剣なという意味です。
そのため、オペラセリアというと広義にはブッファ(喜劇)に対する言葉として
まじめなオペラ全般を指して言うこともありますが、
本来のオペラセリアと言うのは、18世紀のイタリアを中心に発展した、オペラを指しています。
その特徴は
- 高貴である
- 歴史上の英雄や、王、皇帝が題材になっている
- イタリア語で書かれている
- レチタティーヴォとアリアのコントラストがはっきりしている
- 結末がハッピーエンド
など。
もちろん、この時代のオペラセリアすべてにこの特徴があてはまるわけではありませんし
他の時代や他の地域のオペラにも、これらの特徴は多くみられます。
また、時代が進むうちにのオペラセリアの様式は微妙に変化していったようです。
とはいえ、オペラセリアと呼ばれるオペラは、かなり似たようなオペラになってしまっていました。
次第に調まで決まってきて、明るいシーンではニ長調、
悲しいシーンはニ短調といった具合にパターン化されていったようです。
18世紀全盛を迎えたそんなオペラセリアが、時代とともに徐々に飽きられていった理由の一つには、
ストーリーのマンネリ化、そして音楽のマンネリ化があったことは否めないと思います。
いつの時代もそうですが、同じことをずっとやっていると飽きられてしまうのは当然かもしれません。
メタスタージオの台本
オペラセリアを語る時に避けられないのが、メタスタージオという台本作家の存在です。
1698年生まれのメタスタージオは18世紀に活躍した詩人で台本作家。
即興で詩を作るのが得意で、その詩はロマンティックで叙情的な作品だったと言います。
オペラセリア時代のメタスタージオは多くのオペラの台本を手がけ、
メタスタージオが書けば成功するという大御所的な存在だったのです。
今で言えば三谷幸喜さんのような存在?
驚くのはメタスタージオの1つのストーリーに対して、複数の作曲家が曲をつくっていたことです。
同じ題のオペラが数多くできていたということです。
しかもそれは数人ではなく何十人もの多くの人により、作曲がなされていた時期もあったようですから、
いかにメタスタージオがオペラ作家として人気があったかがわかりますよね。
例えばメタスタージオが書いた作品の一つに、オリンピアーデというオペラセリアがあります。
現在比較的有名なのは、ベルコレージ作曲のオリンピアーデですが、
このオリンピアーデに対しては、パイジェッロもチマローザも曲を作っています。
またそれ以外にも、たくさんの作曲家たちが曲をつけていたんですね。
なぜそんなにも多くの作曲家たちが、メタスタージオの同じ台本に曲をつけたのかと不思議に思いますし、
また、なぜそれが現在ほとんど上演されることがなくなったのだろうと思ってしまいます。
現在上演されるオペラの中に、メタスタージオの名前を見かけることはほとんどないんですね。
おそらく、現在上演されることが少ない理由の一つは、
当時のオペラセリアが、カストラートの為に作られた作品が多かった、ということがあるのではないかと思います。
当時の台本の特徴として、カストラートを際立たせるようなストーリーになっていたということがあったようなのです。
カストラートの存在
カストラートとは、男の子が12歳頃に去勢することにより変声期で声変わりすることなく
高音を出し続けることができる歌手たちのことを言います。
体は大きくなるので、とても力強い高音が出せたと言います。
現在では、そのような行為は禁止されているのでカストラートは存在しません。
でも、オペラセリアがはやった、18世紀はカストラート達の全盛期でした。
オペラセリアの流行と、カストラートの全盛期は重なっているのです。
オペラセリアの舞台というのは、カストラートたちが声と技術を披露する場所でもあったので、
オペラセリアの人気は、歌手ありきだったわけです。
だからメタスタージオの同じ話で、多くのオペラが作曲されたのだなと納得できる気がするのです。
おそらく、カストラートのアリアの部分以外は、ストーリーを含めそれほど重要ではなかったのではないでしょうか。
カストラートが演じるのは、英雄的な男性の役。
カストラートのアリアにはカデンツァもついて、朗々と声と技量を披露するカストラート達。
それを聞いて、ファンたちが熱狂していたのだと思います。(生の声はもう聞けないけど聞いてみたい気はします)
映画にもなった有名な「ファリネッリ」というカストラートも、メタスタージオの書いたオペラを歌っています。
このように、歌手ありきのオペラセリアが蔓延することは、
作曲家にとっては、自分が作りたい曲を自由に作ることができなくなるので、おそらくジレンマを持っていた人もいたのではないかと‥。
モーツァルトとグルック
ただ、当時は王侯貴族の依頼で作曲することがほとんどだったので、
作曲家が自由な形式で、自由に作曲をするということはかなり難しかったと思います。
(現代でもスポンサーありきのところはどの業界にもあるので、状況は似たり寄ったりなのかもしれませんが)
それでも、時代の流れは徐々に変わってきます。
その変革に貢献した一人は、グルックという作曲家でした。
グルックは、歌手が声と技術を誇示する歌手ありきのオペラではなく、オペラ全体に音楽的な意味を持たせるような作品を作ったのです。
有名な作品は、オルフェオとエウリディーチェというオペラ。
またグルックは、レチタティーヴォについてもセッコと呼ばれるチェンバロなどを使った方式から、
より音楽性をもたせる、アッコンパニャート(伴奏付きレチタティーヴォ)にしました。
レチタティーヴォにも音楽性をもたせたんですね。
そして、アリアに技巧を過度に組み込むこともしませんでした。
芝居と音楽と歌が絡まりつつ、融合しつつオペラを作り上げる、
のちのワーグナーの形式の先駆けになったと言われています。
とはいえ、グルックの時代もオペラ界では、因習的なオペラセリアが依然として優位だったことは間違いないでしょう。
そして、この時代にはモーツァルトもいました。
モーツァルトは、このオペラセリアの力がまだまだ強かった狭間の時代に、わがままな依頼者の意向に添いつつ、
よくこれだけの名作を残せたものだと思ってしまいます。
やはりそこがモーツァルトのすごいところかなと。
モーツァルトはドイツのザルツブルク生まれですが、彼のオペラは圧倒的にイタリア語のオペラが多くなっています。
また、亡くなる最後の年に書いた作品は
の二つなのですが、この二つは全く異なるオペラです。
魔笛は、地声のセリフが入るジングシュピールという形式で言葉はドイツ語、物語はおとぎ話風。
皇帝ティートの慈悲の方は、メタスタージオの台本を元にした典型的なオペラセリアの形式。
なぜモーツァルトは18世紀も終わりに来る頃に、
すでに人気が衰えてきていた古臭い形式のオペラを書いたのかという気がしますが
式典の為に依頼されての作曲ですから、そこは仕方ないのでしょう。
それでもさすがモーツァルトが作曲しただけあって、音楽は美しくて、
ほとんど上演されなくなってしまったメタスタージオの作品の中で、
現在残っている、数少ない作品の一つなんですね。
やはりこれはモーツァルトの音楽の良さのおかげかもしれない‥と思ってしまいます。


ザルツブルクの街並み
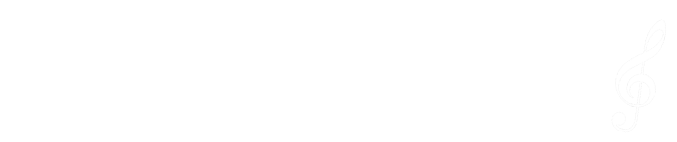
コメントを残す