オペラでファウストといえばグノーが作ったオペラ「ファウスト」が有名なのではないかと思いますが、このオペラの原作はゲーテのファウストです。
今回は原作のファウストってどんな話で、オペラと原作はどんなところが違うのかについてちょっと書いてみようと思います。
オペラは原作のファウストの第1部だけ
ゲーテのファウストを読んだことがあるでしょうか。
私の場合、知っていたものの実際に読んだのは生のオペラを見てからでした。
比較的最近のことです。
グノーの「ファウスト」というオペラをみて、原作も読んでみたくなったんですね。
もっと言うと、順番としては
- 小説「オペラ座の怪人」(ガストン・ルルー)を読んで
- ミュージカルの「オペラ座の怪人」を見て
- その中に出てくるオペラ「ファウスト」を見て→
- オペラの元になったゲーテの「ファウスト」を読んだ
とこんな順番です(私の順番なんか、どうでもいいですね笑)
さて、グノーのファウストというオペラは、1859年にパリのリリック劇場というところで初演されましたが、
初演の時はセリフのあるオペラ・コミックと呼ばれるスタイルでした。
レチタティーヴォではなくセリフがあるオペラです。
ドイツでいうところのジングシュピールですね。
その後ファウストは人気が出たので、セリフの部分をレチタティーヴォにして、更にバレエも入れて、
グランドオペラスタイルにして上演されました。
場所はパリ・オペラ座です。
当時のパリ・オペラ座のスタイルはバレエが入るのが一般的なスタイルだったんですよね。
2019年秋の英国ロイヤルオペラの引っ越し公演がありましたが、その時の上演はこのグランドオペラスタイルのファウストでした。
ファウストというオペラは初演は人気はそれほどでもなかったのですが、その後非常に人気のオペラとなったのです。
それはオペラ好きな人なら見てみるとわかると思うのですが、まあおもしろいのです。
そこで原作ってどうなっているのだろう?と思ったわけです。
オペラの中のファウスト博士はかなり誠実でマルガレーテ一筋に見えるけど、実際のファウストもそうなのか、
マルガレーテはどんな娘で、メフィストフェレスってどんな悪魔なのか
何よりゲーテのファウストってそもそもどんな物語なの?と思って読んでみたわけです。
その結果、原作とオペラを比較してみると、かなりイメージは違います。
私なりに一言で言うなら、
物語としてはオペラの方がおもしろい、というかわかりやすいと感じました。
原作のファウストは大きく第1部と第2部に別れていて、2部が発表されたのは1部から20年以上も後の事。
内容的にも全然違う設定で、皇帝が出てきたりして今でいうなら続編という感じです。
原作はドイツ語の戯曲形式で書かれているのですが、戯曲にしてはかなり長大で、しかも第2部まであるという大作なわけです。
また韻文形式になっていて、諸所に詩のような箇所が出てきます。
韻文というとロシアの作家プーシキンを思い出します。
エウゲニー・オネーギンというチャイコフスキーのオペラは韻文形式のセリフが多く使われているオペラなんですよね。セリフが美しいと言われているオペラでもあります。
グノーのファウストは原作のうち第1部の方を元にします。
原作第1部では、ファウストはマルガレーテに恋するのですが、オペラの方でもこの二人の恋が軸になっています。
ちなみに原作第2部の方ではファウストはギリシャ神話のヘレナという美女と恋に落ちるのですが、
最終的には第2部でマルガレーテの魂に救われるので、
厳密にいえばオペラの一番最後の部分は第2部の最後の部分をイメージしているのかなと思います。
これは私の個人的意見ですが‥。
原作とオペラの違いって何?
オペラは老人ファウストが若返りの薬を飲んで、熱烈な恋をするのですが、そのせいで妊娠したマルガレーテは不幸へと転落していくという、現代でもありそうな物語が軸になっています。
悪魔のメフィストフェレスは、ファウストを若くしたり、宝石箱を用意したり、決闘でファウストを勝たせたりと恋の手伝いをしているものの、
主軸は二人の恋と破滅であって、悪魔の世界というイメージはあまりなく、
しいて悪魔らしいところといえば、メフィストフェレスが第二幕で魔術でワインを出すあたりではないかと思います。
あとはワルプルギスの夜をイメージした第5幕バレエのところですね。(バレエがあれば‥。バレエは舞台によってない場合もあると思います)
ところが原作を読むと、ファウストとマルガレーテの恋と破滅は意外にあっさりである事に気がつきます。
その代わり天上の序曲と称する悪魔達の世界や、若返り薬を作る魔女の家のシーン、そしてワルプルギスのシーンがどちらかというと主で、細かい描写だしとても長いです。
オペラはかなり普通の恋愛悲劇の色が強いけど、原作はおとぎ話感が強いとでもいうのでしょうか。
それ以外にも原作との違いはちょいちょい感じるところがありますし同じところも。
例えば、往来で初めてファウストがマルガレーテに声をかけた際、マルガレーテは
「私はお嬢様ではありませんし、美しくもありません、お供がなくても一人で帰れます」と答えます。
これについてはオペラは原作通りのセリフです。
オペラではあたかも清純な若い二人が恋に落ちると言う印象なのですが、
原作のマルガレーテはまだ14歳を過ぎたばかりの少女で、オペラでは成熟した女性が演じるから原作がそこまで若いとはわからなかったです。そこはちょっとした違い。
また、オペラではファウストは恋に弱気に見えますが原作のファウストはちょっと違います。
オペラでは、宝石で気を引くようにいうのはメフィストフェレスですが、原作ではファウストが積極的に指示しているんですよね、しかも1度ではなく2度とも。
どちらかというと狡猾。
また、すぐにでも口説きたいというファウストに対して、
「物事には手順ってものがある、短気は損気」と逆に諌めるのも悪魔の方なのです。
その言い方はちょっと気持ち悪いのですが(笑)
つまり見た目は若くても心は老練なファウストにとって、幼いマルガレーテに言いよるのは赤子の手をひねるより簡単な事だったわけです。
オペラも原作でもマルガレーテは天使のような少女。そして彼女はメフィストフェレスの怖さにも気づいています。
「空はあんなにも美しく丸い円を作り、キラキラ輝きながら永遠の星がのぼる‥君の目を見つめていると‥」と、言葉たくみにファウストが話すのに対しマルガレーテは不安を覚えていて、
「とても上手な言い方は牧師さんのようだけど少し違う、何か変、ずっと嫌だった、一緒にいる人(メフィストフェレスのこと)、あの人がいるだけで血が凍る」と。いかにもゲーテっぽい言い回しかな。
ファウストが真にマルガレーテに恋しているのはわかるものの、原作では
森でメフィストフェレスと過ごす不思議なシーンがあり、気が付くともうすでにマルガレーテとは別れたのか、破滅への道へといっているんですよね。
そもそもファウストは仮の若い姿だからなのか、二人の別れのシーンも特に記述が無く、
いつの間にか母は死んでいたり‥。ちょっと不思議。
また決闘のシーンはどちらもありますが、
原作ではマルガレーテはいつの間にか子供を産んで、我が子を殺して、牢屋に入っていると言う事実がすでに起きた事として次々とさらりと書かれていると言う印象なのです。
そうそう、オペラでは最初から母はすでに亡くなっていましたが、
原作では生きていて(登場はしないけど)マルガレーテが妊娠した事で苦悩で死んでしまうとなっているんですよね。これも違うところ。
あと若返りの薬ですが、これを作るシーンが原作ではかなり長いです、ここにこんなにページを割いていたのねという感じ。
それが魔女の厨の場面で、オペラにはないし、そもそもオペラでは最初にファウストは若く変身しちゃいますが、原作では広場でのシーンの後です。
つまり広場でのシーン(原作では酒場)はファウストはまだ老人のままなんですよね。
広場でメフィストフェレスが酒場の各テーブルに穴を開けて、魔術でそこからワインを溢れださせるのですが、ここをどんな風にするかはオペラの演出次第だと思います。
それとマルガレーテに思いを寄せるジーベルと言う若者ですが、オペラでは控えめでおとなしい役でメゾが演じますが、原作では血気盛んな若者です。挑発したりナイフでつっかかったりするタイプ。
なので、ちょっと違うキャラクターだなという感じですね。
酒場のシーンの後に行くのが魔女の家で、そこでグツグツと若返りの薬や乞食スープとやらを作っているわけです。
作っているのは尾長猿たちというのもなんともおとぎ話のような世界。
魔法の鏡にマルガレーテが映っている様子は、なんだか不気味なグリム童話のようです。
ちなみにオペラを見る時にはメフィストフェレスの衣装と足にも注目するといいかもしれません。
原作ではかなりはっきりと衣装が書いてあって
- 最初に登場する時は遍歴学生といった身なり
- 次に登場する時は黄金の刺繍入りの赤い上着に裾が短いマント。
また片足は馬の蹄で、変な歩き方をしている。となっているんですよね。
(もともと悪魔には角と尻尾と蹄があったけど、文明が広まり蹄だけ残ったということらしいです)
そのあたりオペラではどうなっているのかはちょっと注目すると楽しいところかも。
と言うように、原作のファウストは怖いおとぎ話の色が濃い一方で、二人の恋の顛末はいまいち明瞭ではないのですが、
オペラの方では魔女とか、怖いおとぎ話のような部分は省かれ、地上の恋愛物語としてわかりやすくなっているというそんな印象です。
とはいえ原作はゲーテならではの言葉とか哲学があって、その良さはオペラとはまたちょっと別物だなと思います。
原作ゲーテのファウストのおもしろさって
例えば、ファウストの事を言っている悪魔達の会話ですが、
「湧き立つ心はただ遠くを憧れ、
天の星から一番きれいなのをとりたがり、
地上では喜びをあまさず欲しい
思いがあれば迷うもの、それが人間だ」(集英社文庫ファウスト・池内紀訳より)
と言われ、
「あやつの心を根っこからもぎとって、好きなように引きまわすがいい」(同 ファウストより)
と言われてしまうところなど、まさに人間の欲を諭されているような気がするのは私だけでしょうか。
また、宝石のくだりの僧侶の悪徳ぶりががおもしろいんですよね。
わけのわからない宝石をもらって心配した母親は僧侶を呼んでくるわけです。
僧侶はほくほくと宝石を持って行ってしまうんですが、その時の言い草がひどい。
「全くもって良い事を思いつかれた、教会は丈夫な胃袋を持っており何を食べても腹を壊さない」と
宝石はつまらぬものだとこき下ろしていただいていき、
お礼ときたら「天国でのご褒美を約束する」というもの。
思わず笑ってしまうような強欲な僧侶なのですが、母も娘の納得してしまうからどうしようもない、
そしてそれをメフィストフェレスに言わせているんですよね。
すごい風刺だなあと。
オペラにはそんな僧侶は出てこないし母親も出てこないんですけどつい笑ってしまった部分でした。
隣家のマルタとメフィストフェレスの不思議な関係は、オペラにもあって私としては意味不明の箇所なんですけど
原作も似たような印象です。やはり不思議。
マルタは夫が死んだと聞いても悲しみより、何か金貨か宝石を自分にことづけなかったのかと聞くような女性で、なんだかなあと思う夫婦関係です。
これも夫婦関係の風刺なんだろうか。
そしてもう一つ、マルガレーテが言う言葉で
「人様は口で褒めても、心では見下している。お金がなければ何もならない。貧しければ所詮はどうしようもない」(同じく集英社文庫ファウスト・池内紀訳より)
と言うところ。ちょっと辛い言葉ですが、
結果として宝石を見てしまったマルガレーテは、ファウストの本質を見抜く目を曇らせてしまったのかもしれないです。
最後にオペラ「ファウスト」をもっと知りたいなら、ガストン・ルルーの「オペラ座の怪人」を読むのもぜひおすすめです。
パリ・オペラ座の事やオペラ「ファウスト」の事がが出てきて、しかもかなり実際の人物をモデルにしていておもしろいです。
グノーの「ファウスト」悪魔登場!・解説オペラ座の怪人にも出てくるオペラ
↑こちらもよければどうぞ
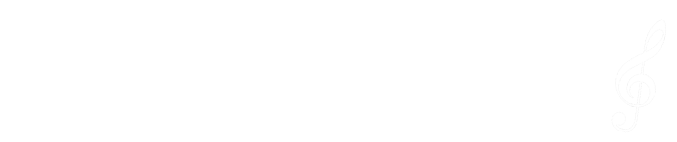

コメントを残す